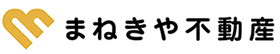弁護士が解説:相続にまつわるトラブル事例と対策 第1回

相続は、人生において避けられない出来事の1つですが、多くの人が「うちは家族仲がいいから大丈夫」「うちには大した財産はないから揉めるはずがない」などと考えてしまい、事前の準備を怠りがちです。
しかし、実際の相続トラブルの多くは、「仲の良い家族」や「財産がそれほど多くない家庭」でも発生しています。
そこで、今回は、実際にあった典型的な相続トラブルを3件ご紹介し、それぞれの背景と法的ポイント、そしてそこから得られる教訓について詳しく解説します。
1 事例1:「母が介護したのに、遺産は平等?」~介護と寄与分をめぐる兄弟の対立
1つめの事例は、被相続人の介護に貢献した相続人が、その貢献度を巡って他の相続人と対立する「寄与分」に関するトラブルです.
1-1 背景となる事情
このケースでは、父が亡くなり、相続人は長男、次男、長女の3人でした。母はすでに他界していました。
父の遺産は、自宅不動産(評価額2,000万円)と預貯金1,000万円で、遺言書はありませんでした。
父の晩年の介護を主に長女が担っていました。長男夫婦は遠方に住んでいたため、長女は10年間、買い物や通院の付き添い、生活支援などを継続的に行っていました。その献身的な介護は近所でも知られており、「娘さんがずっと面倒を見ていた」と評判でした。
1-2 トラブルの発生
相続が開始されると、長女は自身の介護の貢献を理由に「私は父の介護をしてきたから、その分多くもらいたい」と主張し始めました。
これに対し、長男と次男は、長女への感謝は示しつつも、「遺産は法律上、兄弟で平等に分けるのが基本だ」と反発しました。双方の主張は平行線をたどり、感情的な言い争いに発展しました。結局、話し合いでは解決に至らず、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる事態となりました。
1-3 法的ポイント:寄与分とは
このケースで主要な争点となったのは、民法に定められている「寄与分」です。 寄与分とは、被相続人の療養看護や事業への貢献など、特定の相続人が被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした場合に、その貢献度に応じて通常の法定相続分を超えて遺産を取得できる制度です。
ただし、寄与分が認められるにはいくつかの要件があります。具体的には、①その貢献が無償であること、②一定期間継続して行われたこと、③特定の相続人に限定された貢献であることなどが挙げられます。
今回の長女の介護は、医療的な専門性はなかったものの、長期間かつ継続的な支援であったことから、一定の寄与が認められました。
調停の結果、家庭裁判所は長女に対して寄与分として300万円の上乗せを認め、最終的に長女が1100万円、長男と次男がそれぞれ950万円を取得するという内容で遺産分割が成立しました。
1-4 教訓:介護の貢献は法的に評価され得る
この事例から得られる重要な教訓は、親族間では「当然のこと」と見なされがちな介護の貢献も、法的には「寄与」として財産分与に反映される可能性があるという点です。
相続トラブルを避けるためには、被相続人が生前に家族と介護の貢献について協議し、その意思を遺言書などで明確に示しておくことが非常に有効です。これにより、感情的な対立に発展するのを未然に防ぐことができます。
2 事例2:「父の口約束が信じられない!」~生前の言動と遺言書が食い違ったケース
2つめの事例は、被相続人の生前の口約束や言動と、亡くなった後に発見された遺言書の内容が食い違い、トラブルに発展したケースです。
2-1 背景となる事情
このケースでは、父が亡くなり、相続人は妻と2人の息子でした。父は生前、長男に対して「この家はお前が継げ」とたびたび口にしていました。長男もその言葉を信じ、父と同居し、実家のリフォーム費用を自費で負担するなど、家を継ぐ意思を示していました。
しかし、父の死後に開封された遺言書には、驚くべき内容が記されていました。 「不動産と預金は全て妻に相続させる」と明記されており、長男の名前は一切記載されていなかったのです。
2-2 トラブルの発生
遺言書の内容を知った長男は、「父は生前、自分に家を譲ると言っていたのに、遺言書の内容は納得できない」と強く主張しました。
一方、母と次男は、「法律上も、遺言通りに進めるべきだ」として長男の主張を退けました。話し合いは進まず、長男は自身の「遺留分」を侵害されたとして、「遺留分侵害額請求」を検討することになりました。
2-3 法的ポイント:遺言書の優先と遺留分
この事例における法的ポイントは、遺言書の法的効力と「遺留分」の存在です。 遺言書は、原則として被相続人の最終的な意思を示す法的文書であり、正式な様式を備えている限り、口約束や生前の言動よりもその内容が優先されます。つまり、いくら生前に家を譲ると言っていたとしても、正式な遺言書に別の内容が記されていれば、遺言書の内容が法的に優先されるのです。
しかし、遺言によって特定の相続人の取り分が極端に少なくなる、あるいはゼロになった場合、民法で定められた相続人の最低限の取り分である「遺留分」を侵害している可能性があります。
このケースのように、長男に全く相続分がなかった場合、長男は母に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
具体的に、配偶者と子が相続人の場合、子全体の遺留分割合は1/4と定められています。 長男と次男の2人兄弟であれば、長男の遺留分はその1/2、つまり全体遺産の1/8(=500万円)となる可能性があります。ただし、具体的な相続関係によって遺留分の割合は変動するため、ケースバイケースで判断されます。 このケースでは、家庭裁判所を介した話し合いの末、母から長男に対して800万円を支払うことで和解が成立しました。
2-4 教訓:遺言書とコミュニケーションの重要性
この事例が示す重要な教訓は、遺言書の内容が家族の事前の想定と食い違っていた場合、深刻な不信感や感情的な対立に繋がる可能性があるということです。 このようなトラブルを回避するためには、被相続人が生前に家族と相続に関する意思をしっかりと話し合い、合意形成をしておくことが非常に重要です。
また、家族に配慮した遺言内容にしておくことも、トラブル防止の鍵となります。 生前のコミュニケーションと適切な遺言書の作成が、円満な相続を実現するための不可欠な要素と言えるでしょう。
3 事例3:「音信不通の兄が相続を止めてしまった!」~遺産分割協議が進まない共有問題
3つめの事例は、相続人のうちのひとりが行方不明であるために、遺産分割協議が滞ってしまったケースです。
3―1 背景となる事情
このケースでは、母が亡くなり、相続人は3人の子どもでした。遺言書はなく、主な遺産は母名義のマンションと預貯金でした。
次男と長女は遺産分割協議を進めようとしましたが、長男とは20年以上も音信不通で、その居場所も不明でした。
3-2 トラブルの発生
遺産分割は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
不動産を売却して現金に換え、それを分割したいと考えていた次男と長女は、長男と連絡が取れないことで、相続手続きを一切進めることができず、途方に暮れてしまいました。
不動産の処分もできず、預貯金も引き出せなくなり、日常生活にも影響が出かねない状況でした。
3-3 法的ポイント:不在者財産管理人制度
相続人の中に行方不明者がいる場合、民法および家事事件手続法に基づき、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。
不在者が長期間行方不明であっても、死亡が確認されない限りは法的に「相続人」として扱われるため、遺産分割協議に参加させることができない場合、この管理人の選任が必要となるのです。
選任された不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。さらに、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所の許可を得て遺産分割に応じることも可能です。
本件では、家庭裁判所が長男について不在者財産管理人を選任しました。その後、家庭裁判所の関与のもとで適正な遺産分割が行われ、無事にマンションも売却することができました。次男と長女は長年の懸案だった相続問題は無事に解決されました。
3-4 教訓:早期の対応と遺言書による指定
この事例の教訓は、音信不通の相続人がいるだけで、相続手続きが大幅に滞ってしまうという現実です。そのため、相続人の所在を早期に確認し、速やかに対応を始めることが非常に重要です。
また、将来的に家族間の関係が希薄になることが想定される場合や、連絡が取りにくい親族がいる場合は、遺言書で遺産分割方法を具体的に指定しておくことが非常に有効な対策となります。
遺言書があれば、たとえ一部の相続人と連絡が取れなくても、遺言の内容に沿って手続きを進めることが可能になるため、遺産分割協議の長期化や複雑化を防ぐことができます。
4 まとめ:相続トラブルを防ぐには?
今回ご紹介した3つの事例から分かるように、相続トラブルは決して特別なことではなく、誰にでも起こり得る身近な問題です。
これらのトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現するためには、以下の3つのポイントが特に重要となります。
4-1 遺言書の作成
遺言書は、被相続人の最終的な意思を明確に示すための最も有効な手段です。 特に、不動産や事業承継に関する遺産がある場合、特定の相続人に多く財産を残したい場合、あるいは相続人間のバランスを考慮して分割したい場合などには、遺言書の作成が必須と言えるでしょう。
遺言書によって、相続人間の不必要な争いを防ぎ、被相続人の希望通りの遺産分割を実現することができます。遺言書には様々な形式がありますが、法律で定められた要件を満たしていないと無効になる場合もあるため、専門家のアドバイスを受けながら作成することが望ましいです。
4-2 家族間のコミュニケーション
生前の家族間の話し合いこそが、相続トラブルを防ぐための最大の鍵です。
家族間で相続についてオープンに話し合い、お互いの考えや希望を共有することで、感情面のもつれが法的な対立に発展するのを防ぐことができます。定期的な家族会議の機会を設けるなど、積極的にコミュニケーションを図ることが大切です。
4-3 専門家への相談
相続は、法律、税務、登記など、多岐にわたる専門知識が必要となる複雑な分野です。遺産分割協議書の作成、相続税の申告、不動産の名義変更など、様々な手続きが伴います。これらの手続きを適切に進めるためには、弁護士や税理士などの専門家への相談が非常に有効です。
専門家は、個々のケースに応じた適切なアドバイスを提供し、より円滑かつ安心して相続を進めるためのサポートをしてくれます。特に、不動産が含まれる相続や、相続人が遠方に住んでいる場合、あるいは海外にいる場合など、手続きが複雑になることが予想されるケースでは、早期に専門家に相談することがトラブルの予防に繋がります。専門家は、法的な観点だけでなく、税務面でのメリット・デメリットなども考慮した上で、最適な解決策を提案してくれるでしょう。