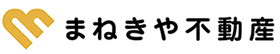弁護士が解説:相続にまつわるトラブル事例 第2回~遺産隠し・名義預金・相続放棄にまつわる深刻トラブル~
 相続は、誰にでも訪れる人生の大きな節目です。しかし、「遺言もないし、財産も少ないから問題ないだろう」と油断していると、ある日突然、「相続」ならぬ「争族」に巻き込まれてしまうことがあります。
相続は、誰にでも訪れる人生の大きな節目です。しかし、「遺言もないし、財産も少ないから問題ないだろう」と油断していると、ある日突然、「相続」ならぬ「争族」に巻き込まれてしまうことがあります。
そこで、今回は、前回に引き続き、より複雑化しやすい相続トラブルの事例として、「遺産の使い込み」「名義預金」「相続放棄をめぐる誤解」の3つのケースをご紹介します。
1 事例1:「兄が遺産を使い込んでいた!」~ 相続開始前の預金引き出しと特別受益の主張
1つめの事例は、被相続人の生前に行われた預金の引き出しが、相続開始後に「遺産の使い込み」として問題になったケースです。
1-1 背景となる事情
このケースでは、母が亡くなり、相続人は長男と長女の2人でした。母の遺産は、自宅不動産と預貯金約2000万円で、遺言書は作成されていなかったため、相続人同士の協議によって遺産分割を行うことになりました。
しかし、長女が母の預金通帳を確認したところ、母が亡くなる直前の数年間にわたり、長男が頻繁にATMから現金を繰り返し引き出していたことが判明しました。その合計額は約800万円にも上り、長女はこれを「遺産の使い込みだ」として憤りを覚えました。
1-2 トラブルの発生
長女からの指摘に対し、長男は「母の生活費のために引き出しただけで、自分が個人的に使ったわけではない」と説明しました。しかし、長女は「生活費にしては金額が多すぎる上、使途を証明するレシートや記録も一切ない」と疑念を深めました。
結局、両者の話し合いでは解決に至らず、長女は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるに至りました。
1-3 法的ポイント:使い込みと特別受益の立証
このようなケースでは、実際に「使い込み」があったかどうかを立証することが非常に困難であり、事実認定が主な争点となることが多いです。
もし、長男が母から生前に贈与を受けていたことが証明されれば、それは民法第903条に規定される「特別受益」に該当し、長男の法定相続分からその分が控除される可能性があります。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって特別に利益を受けていた場合に、公平な遺産分割を実現するために、その利益を相続財産に加算して計算する制度です。
また、相続開始前の預金引き出しは、「使い込み」として不法行為に該当する可能性もあります。
調停や審判の場では、預金引き出しの使途、その頻度、具体的な金額、そして領収書やその他の記録といった証拠書類が詳細に検討されることになります。
本件では、長女側からの明確な証拠が不十分であったため、裁判所は長男の引き出しを「生活費として相当な範囲であった」と判断し、遺産分割において大きな調整は行われませんでした。
しかし、この判断は長女の不信感を完全に解消するものではなく、兄弟間の関係にしこりが残ってしまいました。
1-4 教訓:生前の記録と証拠保全の重要性
この事例から得られる教訓は、被相続人の生前に行われた預金の引き出しは、その使途や意図に関わらず、後になって相続トラブルの火種となり得るということです。
親の介護費用や生活費のために預金を管理したり、買い物代行などでお金を扱ったりする場合には、後日の疑念を避けるためにも、以下の点に特に注意し、記録を残すことが非常に重要です。
ア 領収書やレシートの保管
イ 支出内容の詳細なメモ
ウ 写真や動画による記録
エ 通帳の管理
オ 家族間での情報共有
これらの記録を怠ると、たとえ正当な理由での引き出しであっても、後から使い込みを疑われ、立証に多大な労力を要することになります。円満な相続のためには、被相続人の生前から金銭管理の透明性を確保することが不可欠です。
2 事例2:「名義は父だけど、このお金は私のもの!」~名義預金をめぐる兄妹の対立
2つめの事例は、被相続人名義の預金口座に、実質的には相続人自身の資金が含まれていた場合に生じる「名義預金」に関するトラブルです。
2-1 背景となる事情
このケースでは、父が亡くなり、母はすでに他界していたため、相続人は長男と長女の2人でした。父の遺産は、預貯金1500万円と不動産1件でした。
しかし、その預金のうち800万円が、長女が自身の生活費や資産形成のために、毎月父の口座に預け入れていたお金であることが判明しました。
長女は、「この800万円は父の名義で管理してもらっていただけであり、実質的には私の財産であって、父の遺産には含まれないはずだ」と主張し、遺産分割の対象から除外するよう求めました。
2-2 トラブルの発生
これに対し、長男は、「預金の名義が父である以上、当然に父の相続財産である」として長女の主張を認めず、預金の帰属をめぐって両者は激しく対立することになりました。
最終的に、この問題は家庭裁判所の調停に持ち込まれ、当該預金が父から長女への「贈与」であったのか、それとも長女が父に預けていたお金にすぎないのかが主な争点となりました。
2-3 法的ポイント:名義預金の判断基準
「名義預金」とは、預金通帳などの名義と、実質的な預金が異なる場合の預金を指します。例えば、親が子の名義で預金していた場合や、本件のように子が親の名義で自身の資金を預けていた場合などがこれに該当します。
形式上は親の名義であっても、その実質が子の財産であると認められれば、その預金は相続財産には含まれないことになります。
家庭裁判所では、名義預金の帰属を判断する際に、以下のような様々な要素を総合的に考慮します。
ア 入金経路と源資
イ 通帳や印鑑の管理者
ウ 出金履歴と使途
エ 通帳の保管状況
オ 贈与の意思の有無
本件では、これらの要素が詳細に検討された結果、最終的に裁判所は「当該預金は長女の資金であり、父の相続財産には含まれない」との判断を下しました。この判断により、長女の主張が認められ、800万円は遺産分割の対象外となりました。
2-4 教訓:資産の所有権の明確化
この事例が示す重要な教訓は、相続トラブルを未然に防ぐためには、「誰のお金か」「誰の資産か」を明確にしておくことが極めて重要であるということです。 名義預金に限らず、不動産などの資産についても、その名義と実質的な所有者が一致しているかを確認し、もし異なるのであれば、その所有権を明確化しておくことがトラブル防止につながります。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
ア 贈与の場合は贈与契約書の作成
イ 預かり金の場合は合意書の作成
ウ 定期的な資産状況の確認と見直し
エ 専門家への相談
名義預金かどうかは、資産の所有権を曖昧にしたままにしておくと、相続時に予期せぬトラブルに発展する可能性が高いため、生前の明確化が極めて重要です。
3 事例3:「相続放棄したはずが、債権者から請求が…」~相続放棄と「単純承認」の思わぬ落とし穴
3つめの事例は、相続放棄をしたにもかかわらず、その後の行動によって相続を「単純承認」したとみなされ、故人の債務を負うことになってしまうという、相続放棄に関する誤解やリスクについてのケースです。
3-1 背景となる事情
このケースでは、父が多額の借金を残して亡くなりました。相続人は長男と次男の2人でした。兄弟は、父の借金を相続したくないと考え、協議の上、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てを行い、受理されました。
しかし、長男は、父が住んでいた家にそのまま居住を続けていました。その半年後、父の債権者から長男に対し、「あなたは相続を承認したとみなされるため、借金を返済する義務がある」として、借金の請求が届きました。
3-2 トラブルの発生
長男は「家庭裁判所で相続放棄が認められたはずなのに、なぜ今になって請求されるのか」と困惑しました。一方、債権者は、「長男が被相続人である父の財産を継続して処分・使用していたため、これは民法に定められた『単純承認』に該当する行為であり、相続放棄の効力は失われている」と主張しました。
3-3 法的ポイント:「単純承認」のリスク
民法第921条には、「法定単純承認」という規定があり、相続放棄を検討している相続人が、特定の行為を行った場合には、相続を「単純に承認したもの」とみなされ、相続を承認したとみなされ、放棄の効力が失われる可能性があります。
具体的に、同条が定める単純承認とみなされるおそれのある行為には、以下のようなものが挙げられます。
ア 相続財産の一部を処分・使用した場合
イ 相続財産で自分の借金を返済した場合
ウ 相続財産に手を加えた後に、放棄の申述を行った場合
本件では、長男が相続放棄をした後も、父の住んでいた家に居住を続け、父名義の家具や生活用品を継続して使用していたこと、さらには固定資産税の支払いまで行っていたことなどが重視されました。
最終的に、家庭裁判所での審尋の結果、長男の相続放棄の効果は一部否定され、長男は父の債権者に対して支払い義務を負うことになってしまいました。
3-4 教訓:相続放棄後の行動の慎重さ
この事例から得られる教訓は、相続放棄を検討している、あるいは相続放棄が受理された後であっても、相続財産に手を加えることは非常にリスクが高い行為であるということです。
特に、以下のような行動は、単純承認とみなされ、相続放棄の効力を失う原因となる可能性があります。
ア 故人の住居に引き続き住み続けること
イ 故人の預金通帳からお金を引き出す、あるいは使用すること
ウ 故人の家具や電化製品などの形見分けをすること
エ 故人の税金や公共料金を相続人の名義で支払うこと
相続放棄を検討する際は、申述を行う前の行動はもちろんのこと、申述が受理された後の行動にも細心の注意を払う必要があります。不安な点があれば、相続放棄の手続きを始める前に、必ず弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家は、相続放棄の手続きだけでなく、その後の行動についても具体的なアドバイスをすることができます。
4 まとめ:相続トラブルの「見えにくい火種」に注意
今回ご紹介した3つの事例に共通しているのは、いずれも表面的には分かりにくい「見えにくい火種」が原因となってトラブルに発展したという点です。
これらの事例から分かるのは、相続を「見える化」することがトラブル防止の第一歩になるということです。 具体的には、以下のような細かな配慮と対策が不可欠です。
ア 通帳の管理状況と記録の保管
イ 資産の名義と実質所有者との一致確認
ウ 相続放棄後の財産の取り扱い
これらの「見えにくいリスク」を相続が発生する前から可視化し、適切な対策を講じておくことで、安心して円満な遺産承継を進めることができます。
そのためには、相続開始前から、弁護士や税理士などの専門家に相談しておくことが極めて有効です。
「争続」という不幸な事態を防ぐためには、生前から専門家の助言を受け、計画的に相続対策を進めることが何よりも重要です。早期に専門家に相談すれば、家族の絆を守り、円満な相続を実現できるでしょう。