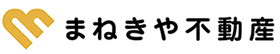相続不動産の相談事例・中央区土地編 第1部
相談内容
ご実家で一人暮らしをしていたご兄弟が亡くなり、築60年の土地建物を相続された方からのご相談です。相続人はご相談者お一人です。
令和3年に相続されたものの、しばらくは何も手をつけられず、「このまま維持するのか、マンションを建てるのか、それとも売却するのか」と悩まれていました。
ご相談者様は70代、ご主人を亡くされており、現在は神奈川県にて娘さん二人と同居。ご近所にご長男もいて、お子様が3人という家族構成でした。
家族それぞれの意向を整理しながら、今後の方針を一緒に考えていく必要があるケースでした。なお相続人はご相談者様お一人です。
相続不動産についてのヒアリング
1-1 お子様の意向
まずはご相談者様のお子様全員にお会いし、お母様が相続された不動産についての意向を伺いました。
結果として、お子様全員が「お母さんの好きなようにしてほしい」との考えで一致していました。
そのため、実質的な判断権を持つお母様の気持ちを丁寧に確認しながら、今後の方針を一緒に検討していくこととなりました。
1-2 相続人の意向
相続人であるご本人様は現在、神奈川県にお住まいで、相続された不動産を遠方から管理していくのは難しいと考えておられました。
そこで当初は、既存建物を解体してマンションを新築し、その後の管理を弊社に任せる方向で検討が進みました。
そのため、まずは建築費用の把握を目的として、建築会社に見積もりを依頼することとなりました。
1-3 建築見積もりとご提案
鉄筋コンクリート造を得意とする工務店2社と、大手建設会社2社に建築の見積もりを依頼し、それぞれのプランと費用感をご相談者様にご提示しました。
工法やコスト、将来的な賃貸需要などの視点から比較検討できるよう、内容を整理したうえでご提案しています。
今後は、建築による活用が本当に適しているのかどうかも含めて、ご本人様にじっくりご検討いただくこととなりました。
1-4 負債と遺産分割の懸念
ご相談者様は、マンション建築にあたり借入を行うことになれば、将来その負債を子供たちに残すことになるのではと、大きな懸念を抱かれていました。
さらに、仮に一棟のマンションを残したとしても、それを3人の子供で公平に分けるのは難しいという悩みもありました。
相続税の納税はすでに完了していたため、今後は急がず、ご家族でじっくりと方向性を考えていただくことになりました。
1-5 空き家管理
相続された都内の不動産について、ご相談者様は遠方にお住まいで日常的な管理が難しい状況でした。
そのため、弊社にて空き家管理をお引き受けすることとなりました。
月2回の巡回を行い、郵便物の回収、室内の換気、水道の通水、敷地内の雑草処理などを実施。
結果として、約2年間にわたり本物件の空き家管理を継続することとなりました。
1-6 売却へ
ご相談から約2年半、弊社では定期的にヒアリングを重ねてきました。
最終的にご相談者様は、相続不動産を売却し、神奈川県内のご自宅近くに戸建を3棟購入し、それぞれのお子様に残したいとのご意向を固められました。
「現金よりも住まいがあれば、困ったときも安心」という、母親としての優しい想いが込められていました。
弊社では3区画の土地を探し、購入後は一旦賃貸に出し、弊社で管理する方向で進めることになりました。
相続不動産売却までの流れ
2-1 売却準備・現地調査
売却に向けて現地調査を行ったところ、ご相談者様が相続された不動産の建物が、隣地の境界線を一部越えて越境していることが判明しました。
添付写真の赤いラインが正式な境界線であり、矢印の箇所が隣地への越境部分です。
東京都内など、昔からの住宅地ではこのような越境は珍しくなく、今回はご相談者様の建物が越境している立場であったため、建物を解体することで越境部分は自然と解消されます。
そのため、土地のみの契約とし、引渡し前に弊社にて解体を行うという流れで、売却を進めることになりました。


2-2 確定測量の実施
本件の土地には、昭和56年作成の古い地積測量図しか法務局に備え付けられておらず、また隣地への越境も確認されたことから、売却前に確定測量を実施することとなりました。
確定測量には通常30万~80万円程度の費用がかかり、基本的には売主様のご負担となることが一般的です。
作業には隣地所有者との立会いや官民境界の確認などを含め、2カ月から6カ月程度を要します。
写真は、前面道路に面する官民境界について、中央区の職員と弊社が依頼した土地家屋調査士が現地で立会い、境界を確認している様子です。
ご相談者様にもご同行いただき、弊社も責任をもって立ち会いました。

2-3 確定測量とは
確定測量とは、隣地との境界線を明確にするための手続きです。
売却前にこの作業を行うことで、「どこまでが自分の土地か」を第三者に示すことができ、買主にとっても安心材料となります。
特に東京都心部や古い住宅地では、古い測量図しか残っていないケースが多く、実際の利用状況と登記簿の面積が異なることもあります。
確定測量では、隣接する土地の所有者と現地で立会い、土地家屋調査士が境界の確認を行います。
これにより、後のトラブルを防ぎ、売却をスムーズに進めることができます。
費用や期間は状況によって異なりますが、不動産を手放す前の「リスク」を取り除く大切な工程です。
2-4 売却へ・価格設定
売却に向けた準備が整い、いよいよ価格の設定に進みました。
今回、ご相談者様の最優先の希望は「将来的に戸建を3棟購入し、それぞれのお子様に残すこと」でした。
そのため、単に高く売れば良いということではなく、売却後に発生する譲渡所得税や、将来の相続時にかかる相続税の納税も見据えたうえで、資金の逆算を行い、価格を設定しました。
また、当該物件の近隣相場や過去の成約事例なども参考にしながら、現実的かつご希望に沿った金額を導き出しました。
取引事例も少なく希少価値が高かった物件なので、それなりの価格設定を行いました。
2-5 売却へ・販売開始
令和7年6月20日より、正式に販売活動を開始しました。
まずは全国の不動産業者が閲覧できる業者間流通サイト「レインズ」へ物件情報を登録し、幅広く情報を共有。
併せて「スーモ」「アットホーム」など一般ユーザー向けのポータルサイトにも掲載し、直接の購入希望者にもアプローチを行いました。
さらに、現地の建物外壁には弊社の連絡先を明記した案内板を設置し、周辺を通行する方々にも物件を認知していただけるよう工夫しました。
また、添付の「販売図面」を作成し、お客様や仲介業者様に配布することで、具体的なイメージを持ってもらえるよう丁寧な販売活動を進めました。

2-6 売却へ・ご契約
令和7年7月、販売開始からわずか1か月足らずで購入申込が入り、ご契約に至りました。
お申し込みいただいたのは、現地の建物外壁に掲示していた弊社の連絡先をご覧になったお客様で、「以前からこの物件が売りに出るのを待っていた」とおっしゃっていました。
地域や環境に強い関心を持っていた方だったため、売主様の想いを引き継いでいただける理想的なご縁となりました。
ご相談当初からのご希望であった「子どもたちに戸建てを残す」という目的に向かって、大きな一歩を進めることができました。
2-7 建物解体
今後は、買主様への引渡しに向けて、弊社と提携している解体業者による建物の解体を行う予定です。
対象の建物は木造2階建て、延床面積およそ100㎡であり、解体費用は150万円〜200万円程度になる見込みです。
解体作業は引渡期日までに完了させる段取りで、売主様に代わり、弊社が責任をもって進行管理を行ってまいります。
以上が、今回の相続不動産売却までの一連の流れとなります。
まとめ
今回のご相談では、相続税の納税など急を要する事情がなかったため、時間的な余裕がありました。
その分、ご相談者様の気持ちにしっかりと寄り添いながら、焦らずじっくりと話を進めることができました。
ご相談者様自身も、時間をかけてじっくり考えることで、納得のいく結論を導き出されたのだと思います。
また、途中で何度かお子様たちにもご参加いただき、家族会議の場を設けました。
全員の意見を丁寧に聞き取りながら方針を固めていくことで、皆が納得したうえで売却に踏み切ることができた、理想的なプロセスだったと感じています。
今後、売却後の資金をもとにどのような不動産を取得していくか、資産の引き継ぎをどのように設計していくか、そのプロセスは「相続不動産の相談事例・中央区土地編 第2部」でご紹介いたします。