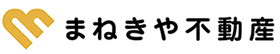相続手続きの流れ:不動産相続で後悔しないために知っておきたいこと
相続は、誰にでも訪れる人生の一大事です。
特に不動産を含む相続では、法律、税金、人間関係など複雑な要素が絡み、放置していると取り返しのつかないトラブルに発展しかねません。
そこで、今回は、「相続手続きの流れ」を中心に、相続にかかる税金の基本や、不動産相続でトラブルが起こりやすい理由などについてわかりやすく解説します。
大切な財産を円満に引き継ぐために、ぜひ参考になさってください。
1 いつまでに何をやるべきか:相続手続きのスケジュールと注意点
相続手続きは、法律上の期限が設けられているものもあり、放置すると大きな不利益を被ることがあります。
まずは、全体の流れと期限を確認しましょう。
相続発生後の主な手続きと期限は以下のとおりです。
1-1 死亡直後から7日以内
死亡届の提出が必要です。死亡診断書を添えて、市区町村役場に提出します。
1-2 1か月以内
葬儀・法要・遺言書の有無の確認を行います。
遺言書がある場合には、それが自筆証書遺言であれば、家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
1-3 3か月以内
相続放棄や限定承認(相続財産の範囲内でのみ負債を相続する手続き)の申述期限が、相続開始を知ったときから3か月となっています。
被相続人に借金があった場合に、その金額に応じて、いずれかを家庭裁判所に申述します。
期限を過ぎてしまうと、単純承認(相続財産と負債を無条件で引き継いだとみなされる)とみなされるので注意が必要です。
1-4 4か月以内
準確定申告という手続が必要です。
準確定申告とは、被相続人に代わって、その年の所得税の申告を行う手続きのことです。
被相続人が個人事業主などで申告義務があった場合に行うことが必要となります。
1-5 10か月以内
相続税の申告・納付が必要となります。
この手続は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に必要となります。
期限が過ぎると延滞税や加算税が科されることもあるので、注意が必要です。
基礎控除の計算方法は次の項目で詳しく解説します。
1-6 おおよそ1年以内
遺産分割協議や名義変更の手続きが必要です。
相続人全員で協議し、合意内容をもとに、不動産の登記や預金の名義を変更することとなります。
1-7 小括
期限付きの手続きが複数あるため、最初の3か月間が特に重要です。
手続きを怠ると、借金まで引き継ぐリスクや、税務署から延滞税を課されるリスクが発生するので、注意しましょう。
2 相続にかかる税金のポイント:知っておきたい基本知識
不動産の相続は、金額が大きくなりやすいため、相続税が発生するケースも少なくありません。
ここでは、相続税の概要とポイントを整理します。
2-1 相続税の基礎控除
相続税はすべての人に課税されるわけではなく、「基礎控除額」を超える遺産がある場合にのみ対象となります。
基礎控除額は、「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で計算します。
たとえば、配偶者と子2人(計3人)が相続人の場合は、「3,000万円 +(600万円 × 3人)」と計算式となるため、 4,800万円までが非課税となります。
2-2 不動産評価の方法と注意点
不動産は「相続税評価額」に基づいて評価されます。
土地であれば「路線価」や「倍率方式」、建物であれば固定資産税評価額が用いられます。
実勢価格(市場価格)よりも低く評価される傾向にあるため、現金よりも相続税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、以下のような注意点があります。
ア 複数人で不動産を共有すると、将来的な売却や分割が困難になります。
イ 賃貸物件など収益不動産は「小規模宅地等の特例」など節税制度が活用できますが、適用要件が細かいため専門家の助言が不可欠です。
2-3 相続税の納付方法
相続税は、原則として現金一括納付ですが、一定条件のもとで以下の方法による納付も可能です。
2-3-1 延納
5年~20年の分割で納付する方法です。
ただし、利子税がかかるため、納付額が大きくなります。
2-3-2 物納
現金での納付が困難な場合、不動産などの財産で納めることができる場合があります。
ただし、要件が厳しいので注意が必要です。
3 なぜ不動産相続はトラブルのもとになりやすいのか
相続をめぐるトラブルの中でも、不動産が絡むケースでは、特にトラブルが深刻化しやすい傾向にあります。
その理由をいくつか見ていきましょう。
3-1 「分けにくい」ことが争いを生む
現金や預金と異なり、不動産は簡単に分割できません。
「長男が住み続けたい」「二男は売却して現金化したい」など、相続人ごとに意見が分かれると、遺産分割協議が長期化します。
共有にしたままでは、管理や税金の負担、売却の合意などに支障が出ることも多く、感情的な対立に発展するケースも少なくありません。
3-2 評価額と実勢価格に差がある
不動産の相続税評価額は実際の売却価格とは異なるため、「相続税はそれほどかからなかったのに、いざ売ろうとしたら全然買い手がつかない」といった問題もあります。
反対に、相続時に思ったより税金がかかり、納税資金が用意できずに困ることもあります。
3-3 遺言書がないと争いが起きやすい
遺言書がない場合、すべての遺産は法定相続分にしたがって分けることになりますが、不動産については「誰が取得するのか」まで明確にしないと実際の手続きが進みません。
被相続人が「長男に家を継いでほしい」と思っていても、それを明文化していなければ他の相続人が納得しない場合があります。
4 相続対策は「生前」から始めるのが鍵
相続手続きは、時間との戦いであると同時に、家族間の信頼が試される場面でもあります。
中でも不動産の相続は、不動性(場所が固定されている)、分割しにくい、価格が高額といった特性のために、トラブルの火種を抱えやすいといえます。そのため、事前の準備が何より大切です。
被相続人にとっては、遺言書を作成し、資産の整理をしておくこと、相続人にとっては、相続が始まった時点で早めに専門家に相談し、必要な手続きを滞りなく進めることが、安心で円満な相続につながります。
不動産を含む相続でお悩みの方は、税理士や司法書士、弁護士などの専門家と連携しながら、早めに行動を起こすことをおすすめします。