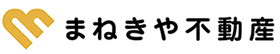遺産分割の調整と交渉に関する弁護士の役割
遺産相続は、残された家族が故人を偲び、絆を再確認する大切な機会であるはずです。しかし、実際には、相続を巡る争いが家族の間に深い亀裂を生み、「争族」と化してしまうケースが後を絶ちません。
町田市においても、こうした相続トラブルの相談が年々増加しています。
なぜこのような問題が起こるのでしょうか。その背景には、故人の財産に対する認識の違い、感情的な対立、そして法的知識の不足があります。
相続財産は、故人の思いが込められた大切なものです。にもかかわらず、その分配を巡って兄弟姉妹が激しく対立し、長年の信頼関係が崩壊してしまうことも少なくありません。
このような事態を避けるためには、専門家である弁護士への相談が不可欠となります。
弁護士は単に法律を適用するだけでなく、相続人それぞれの感情に配慮しながら、公平かつ円満な解決へと導く重要な役割を担います。
そこで、今回は、遺産分割における弁護士の具体的な役割と、その必要性について詳しく解説します。
1 遺産分割の基本知識
遺産分割を進める上で、まずは、その基本的な手続きと法律の枠組みを理解することが重要です。
1-1 遺産分割のステップ:協議、調停、審判
遺産分割は、原則として遺産分割協議から始まります。これは、相続人全員が話し合い、遺産の分け方について合意を目指すものです。故人の遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従うことになります。しかし、遺言書がない場合や、遺言書の内容が不明確な場合には、相続人全員の合意が必要です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は、調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を聞きながら、合意形成を促す手続きです。裁判所という第三者が介入することで、冷静な話し合いの場を設けることができます。
それでも合意に至らない場合は、遺産分割審判へと移行します。これは、最終的に裁判官が、法律に基づいて遺産の分割方法を決定する手続きです。審判となると、当事者の意向よりも法律的な判断が優先されるため、納得のいかない結果となる可能性もあります。
その場合は即時抗告という不服申立ての手続をすることが可能です。
即時抗告は審判書の謄本が送達されてから14日以内に、家庭裁判所に対して申し立てます。

1-2 民法が定める法定相続分と遺言の効力
民法は、遺言書がない場合の遺産の分け方として法定相続分を定めています。たとえば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。この法定相続分はあくまで目安であり、必ずしもそれに従う必要はありません。
一方で、遺言書で定められた遺産の分配割合は、法定相続分に優先します。故人の意思を尊重するため、遺言書に記載された内容が遺産分割の基本的なルールとなります。
しかし、他の相続人が遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に法律上認められている最低限の相続権)が侵害されているような場合には、遺留分侵害額請求の問題が生じることがあります。
1-3 特別受益と寄与分の考え方
遺産分割を複雑にする要因として、「特別受益」と「寄与分」があります。
特別受益とは、特定の相続人が生前に故人から受けた、多額の贈与や遺贈などを指します。たとえば、親の生前に自宅購入資金の援助を受けていた場合、その金額は特別受益として遺産に持ち戻して計算されます。
一方、寄与分とは、特定の相続人が故人の財産の維持や増加に特別に貢献した場合に、その貢献分を考慮して遺産分割を行うことです。たとえば、長年、故人の介護を無償で行っていた場合などがこれにあたります。
これらの要素が絡むと、遺産の評価や分割方法が複雑化し、当事者だけでは解決が困難になります。
2 弁護士が担う役割:全体像
遺産分割における弁護士の役割は多岐にわたりますが、大きく分けると以下の3つに集約されます。
2-1 法律の専門家としてのアドバイスと法的整理
遺産分割には、民法をはじめとする様々な法律知識が必要です。遺言書の有効性、特別受益や寄与分の主張、不動産の評価、相続税の計算など、専門的な知識がなければ正確な判断はできません。弁護士は、これらの複雑な法律問題を整理し、依頼者に適切なアドバイスを提供します。これにより、誤った判断や不利益な合意を避けることができます。
2-2 交渉のプロとしての仲介と調整
遺産分割協議では、感情的な対立が交渉を難航させることが少なくありません。弁護士は、当事者間の間に立ち、冷静な議論を促すことができます。
それぞれの主張を客観的に評価し、公平な解決策を提示することで、対立の激化を防ぎ、合意形成をサポートすることが可能です。
2-3 感情的な対立を避けるための第三者としての役割
長年の家族関係ゆえに、感情的なしこりが遺産分割協議に持ち込まれることもよくあります。
弁護士は、特定の相続人と利害関係のない第三者として、公平な視点から問題を捉えることができます。感情的な対立を客観的な法律問題に置き換え、円満な解決を模索することが可能になります。
3 遺産分割の各段階における弁護士の具体的な業務
以下では、遺産分割における弁護士の具体的な業務を、問題の段階ごとに解説していきます。
3-1 遺産分割協議の段階
遺産分割協議は、弁護士が最も活躍する場面のひとつです。具体的には、以下のような業務を行います。
3-1-1 遺産の範囲と評価の確定
故人の財産には、預貯金や不動産だけでなく、株式、生命保険、美術品、骨董品など様々なものが含まれます。弁護士は、これらの遺産を正確に特定し、専門家(不動産鑑定士、税理士など)と連携して適正な評価を行います。
3-1-2 特別受益・寄与分の主張・立証
特別受益や寄与分は、主張する側がその事実を証明しなければなりません。弁護士は、過去の預金履歴、医療費の領収書、介護記録など、証拠を収集・整理し、依頼者の主張を説得力のある形で提示します。
3-1-3 公平な分割案の作成と提案
弁護士は、法定相続分や特別受益、寄与分などを考慮し、法律と当事者の意向を踏まえた公平な分割案を作成することが可能です。これにより、相続人全員が納得しやすい解決策を見つけ出すことができます。
3-2 交渉・調整の段階
協議が難航した場合、弁護士は以下のような調整を行います。
3-2-1 相続人全員の意向の把握と代替案の提示
各相続人が何を望んでいるのか(現金、不動産、思い出の品など)を丁寧にヒアリングし、それぞれのニーズを満たすための代替案を提示します。
3-2-2 感情的な対立の緩和と冷静な議論の促進
直接の対話が困難な場合、弁護士が窓口となり、互いの主張を冷静に伝えます。これにより、感情的な衝突を回避し、理詰めの議論を可能にします。
3-2-3 相手方弁護士との連携と駆け引き
相手方が弁護士を立てている場合、弁護士同士が法律に基づいて交渉を行います。そのため、感情を排したスムーズなやり取りが可能となります。
3-3 遺産分割調停・審判の段階
協議や交渉が不成立に終わった場合でも、弁護士は依頼者の代理人としていかのような活動を行います。
3-3-1 裁判所への申立て手続きの代行
調停や審判の申立てには、多数の書類作成と手続きが必要です。弁護士はこれらの煩雑な手続きをすべて代行し、依頼者の負担を軽減することができます。
3-3-2 調停委員とのやり取り
弁護士は、調停の場で依頼者の主張を明確に説明し、調停委員の意見を適切に依頼者に伝えます。
3-3-3 証拠収集と主張の整理
審判では、客観的な証拠が非常に重要となります。弁護士は、依頼者に有利な証拠を収集し、これに基づいた主張を行います。
3-3-4 審判における代理人としての活動
審判では、弁護士が依頼者の代理人として、裁判官に主張を述べ、質疑応答に対応します。

4 弁護士を選ぶ際のポイント
遺産分割を依頼する弁護士は、誰でも良いというわけではありません。依頼する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントを抑えておきましょう。
4-1 相続案件の経験と実績
相続は専門性の高い分野です。相続案件の解決実績が豊富で、最新の判例や税務知識にも精通している弁護士を選びましょう。
4-2 相性
弁護士は、依頼者の心の支えとなる存在でもあります。話をじっくり聞いてくれ、共感してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
4-3 費用体系の明確さ
依頼する前に、着手金、成功報酬、実費など、費用について明確な説明を求め、後々費用の点でトラブルが起きないようにしましょう。
5 弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで得られるメリットには、以下のようなものがあります。
5-1 専門知識に基づいた適切な解決策の提示
法律の専門家である弁護士は、依頼者が気づかなかった問題点や、より良い解決策を見つけ出すことができます。
5-2 時間と精神的な負担の軽減
遺産分割は、多くの時間と精神力を消耗します。弁護士に一任することで、依頼者は本業や日常生活に集中することができます。
5-3 相続人同士の関係悪化の回避
弁護士が間に入ることで、感情的な対立を回避し、親族間の関係をさらに悪化させることを防ぐことが可能です。
6 依頼後の注意点
弁護士に依頼した後も、円滑なコミュニケーションが重要です。そのためには、以下の点に注意する必要があります。
6-1 弁護士とのコミュニケーションを密にする
弁護士は依頼者の代理人です。進捗状況や今後の見通しについて、定期的に連絡を取り合い、意思の疎通を図るようにしましょう。
6-2 必要な書類や情報の提供を迅速に行う
故人の財産に関する書類や、家族関係の経緯など、弁護士から求められた情報は速やかに提供しましょう。
7 まとめ
遺産分割は、故人から託された最後のメッセージとも言えます。しかし、多くのケースで、それが「争族」の種となってしまうのが現実です。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な遺産問題を解きほぐすだけでなく、感情的な対立を緩和し、家族が無駄な紛争を起こさないよう、重要な役割を果たします。
相続が「争い」ではなく、故人の思いを継ぐ「手続き」となるよう、少しでも不安を感じたら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。早期の相談が、問題解決への最も確実な一歩となります。
まねきや不動産は、町田市を拠点に活動する相続に特化した不動産会社です。
少数精鋭の専門チームが不動産の相続にまつわる手続をワンストップで支援しています。
誰かに相談したいけれど、誰に相談すればよいかわからないという方は、お気軽にご連絡ください。お話を伺って、必要なサポートをいたします。