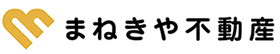相続登記の申請義務化について
自分の近しい方がお亡くなりになり相続が発生をした場合、残された相続人の方がやらなければならない事、もしくは必要であれば手続きを行う必要があることは数多くあります。
その中には期限が定められている手続きも多く、「何から始めればいいのか分からない」という方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
今回は相続が発生をした際の不動産の名義変更(相続登記)について詳しく解説していきます。
1.死亡に伴う基本的な届出・手続
相続が発生し一般的に考えられる手続きの種類のは以下となります。
・死亡届 7日以内
・死体火葬許可申請 7日以内
・世帯主変更届 14日以内
・健康保険証の喪失届 14日以内
・年金受給停止の手続き 10日~14日以内
・相続放棄・限定承認の手続き(必要があれば) 3ヶ月以内
・相続税の申告(必要があれば) 10ヶ月以内
ざっと上げただけでもこれだけの手続きが考えれます。
これにプラスをして、令和6年4月1日から相続登記の義務化という制度が始まりました。
2.相続登記とは
不動産を所有している方がお亡くなりになられた場合に、その名義の変更を相続人等に変える手続きを言います。(登記簿に記載されている所有者の名前を変更する手続き)
この手続きをしておかないと、不動産を売却しようとした場合に、その取引を進めるにあたって支障が出てきてしまいます。
相続登記は、その不動産を管轄する法務局へ申請をする必要があります。
今までは、不動産を所有していた方がお亡くなりになったとしても相続登記をしなければならないという決まりはなく、あくまで当事者の任意とされていました。
その為、相続登記をしなくても特に不利益を被ることが無い方にとっては、登記手続きをせずそのまま放置をしているという方が少なくありませんでした。
これにより、不動産について近年さまざまな問題が発生をしてしまう事態となっていました。
3.相続登記義務化前の問題点
近年、特に地方部では、都市部への人口の流出や、高齢化により未使用の土地がそのまま放置され、その所有者について相続が繰り返され、相続人がねずみ算式に増えっていってしまい、その土地の現在の所有者は一体誰であるのかが不明となっている土地が多く出てきてしまいました。(所有者不明土地問題)
これにより、土地の管理がされずそのまま放置されたり、その土地を国などの行政が公共事業として利用をしようとしても土地の共有者が多数となってしまっている為、なかなか計画が進まず、災害時の復興事業も進められないという深刻な問題へ発展をしてきてしまっていました。
この様な、所有者不明土地の面積は日本全国で九州の面積よりも広いと言われています。
そこでこの問題を解消するため国は様々な制度を規定しました。
その中の一つが「相続登記の義務化」となります。
4.相続登記義務化の概要
令和6年4月1日に施行された、相続登記の義務化の内容は以下の通りとなります。
不動産の登記名義人について相続の開始があったときに、次のいずれかの者は、自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務を負う。(改正不動産登記法第76条の2第1項)
そして、この登記義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料対象となります。(改正不動産登記法164条1項)
4-1.正当な理由の具体的ケース
過料を免れる具体的な正当な理由とは以下のケースが考えられます。
①数次相続(被相続人の死亡後、遺産の分割前に相続人が死亡し新たな相続が発生をしてしまった状態)が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍等の書類の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合。
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合。
③相続登記の申請義務を負うもの自身に重病等の事情がある場合。
④相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、登記簿への住所の開示が被害者の安全に関わる場合。
⑤相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮をしているために登記に要する費用を負担する能力がない場合。
以上のケースは正当な理由となり得るケースであると考えられます。
なお、正当な理由の判断については、登記官において具体的事情を確認したうえで行われます。
また、登記官が申請義務違反を把握しても、直ちに過料の通知をするわけではなく、あらかじめ申請義務を負う者に催告を実施することとなっています。
4-2.経過措置
施行日である令和6年4月1日前に発生した相続についても相続登記の義務化の対象となり、その期日は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内となります。
つまり、今回の相続登記義務化により1番早い申請の期限は令和9年3月31日までとなります。
5.相続人申告登記
3年以内に相続登記を行わなければならないとのことですが、様々な事情により登記の申請が出来ない場合も考えられます。
例えば
・相続人間で遺産の分割の話し合いがなかなかまとまらない。
・相続人のなかで行方不明の人がいる。
この様な事情がある場合に3年以内に登記の申請を強制するというのは手続き的な負担が大きい為、相続人が申請義務を簡易に履行する事が出来るようにする観点からこの「相続人申告登記」の規定が設けられました。
5-1.相続人申告登記の概要
相続人申告登記は不動産の所有者について相続が開始したこと、自らその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度であり、相続登記とは異なり不動産についての権利関係を公示するものではありません。
あくまで相続人の氏名、住所等を公示するにとどまります。
ですので、相続人申告登記をしたからといって、第三者に対して自らの所有権を主張できるわけではありません。
5-2.「相続登記」と「相続人申告登記」の違い
相続人申告登記は、「まだ相続登記は出来ないけども罰則を避ける為の暫定的な手続き」といえます。
ですので以下のような特徴があります。
・手続きに要する書類が簡易的(申出をする相続人が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本の提出でOK)
・特定の相続人が単独での申出ができる(ただし、申告をした相続人以外の相続人は申請義務を果たした事にはなりません。)
・他の相続人の分も含めて代理での申出が可能。(これにより他の相続人も申請義務をはたしたことになります。)
・費用がかからない。(相続登記は最低でも不動産の固定資産税評価額×0.4%の登録免許税が掛かります。)
ただし、後日遺産分割が成立した際には3年以内に相続登記を申請する必要があります。
これを怠ると10万以下の過料を科される可能性があります。
(ですので場合によっては2度手間となるリスクがあると言えます)
以上を考えると、先々代以上前から相続登記が行われておらず、権利関係が複雑になってしまった場合などのケースは、まず相続人申告登記を入れておくのが良いのではないかと思われます。
この手続きを挟むことで、相続登記の申請までの期間を気にする事なく遺産分割のお話合いを他の相続人と出来る事になります。
5-3.相続人申告登記のやり方
相続人申告登記をするには以下の書類を用意する必要があります。
・申請書(書式は法務局のホームページよりダウンロードが可能です。)
・被相続人が亡くなった事が分かる戸籍
・相続人(申出人)が被相続人の相続人であることが分かる戸籍
(兄弟姉妹相続などの複雑な相続では、専門家に依頼をした方が確実かもしれません。)
・相続人(申出人)の住民票
以上の書類をご準備のうえ不動産を管轄する法務局へ申請をします。
6.まとめ
相続等の義務化は最近始まった制度であるため、まだまだ世間に認知された制度であるとは言えません。
実際、昔に親から相続した不動産について名義変更をせずそのまま放置をしてしまっている方も多くいらっしゃいます。
相続は時間が経過すると、問題がどんどん複雑化をしていってしまい、その解決までに余計な時間と費用がかかってしまいます。
そうなってしまう前に、早めのご自身での対応、または専門家への相談をお勧めします。
まねきや不動産は、町田市を拠点に活動する相続に特化した不動産会社です。
少数精鋭の専門チームが不動産の相続にまつわる手続をワンストップで支援しています。
誰かに相談したいけれど、誰に相談すればよいかわからないという方は、お気軽にご連絡ください。お話を伺って、必要なサポートをいたします。