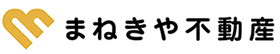配偶者居住権と配偶者短期居住権ってなに?その違いと注意点
私自身もそうですが、夫(または妻)がもし先にいなくなっても今の家に住み続けられるのだろうかという不安を感じたことはありませんか?
2020年の民法改正により、「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」という新しい制度ができました。
これは、亡くなった人と一緒に住んでいた配偶者が、家にそのまま住み続けられる権利です。
今回はこのテーマを掘り下げてみたいと思います。
1.配偶者居住権とは?
夫や妻が亡くなった後でも、配偶者がずっとその家に住み続けられる権利のことです。
たとえば、夫が亡くなり、家の名義が夫の単独名義であったとしても、妻は
「配偶者居住権」を使うことにより、一生その家に住み続けることができます。
1-1.配偶者居住権のメリット
・住む場所が保障される
遺産分割により住む場所がなくなるという心配がなくなり、老後も安心して暮らせます。
・相続しなくても、「住む権利」だけ確保できる
所有ではなく、居住権という形で住み続けられるため、他の相続財産(預貯金など)
を多く相続できる可能性があり、老後の生活資金に回せるかもしれません。
・他の相続人と遺産分割しやすくなる
配偶者居住権を使えば、住むだけの権利と所有権を分けられるので、柔軟な遺産分割が可能となります。
1-2.配偶者居住権のデメリット
・売却、賃貸などが自由にできない
配偶者居住権は「住むことができる権利」なので、自由に売ったり人に貸したりすることはできません。
・所有権が他の相続人にある(共有の場合も)
居住権があっても、たとえばこどもとの共有名義になった場合、リフォームや増改築などの意見が合わずトラブルになる可能性があります。
・配偶者居住権登記の必要性
配偶者居住権は登記しておかないと、第三者に対抗できません。
1-3.配偶者居住権を取得するには
・「遺言」による取得
被相続人が遺言書で配偶者居住権を設定する旨を記載します。
できれば公正証書が望ましいです。
・「遺産分割協議書」による取得
相続人間で、配偶者居住権を与えることを遺産分割協議で合意し、遺産分割協議書にその旨を記載します。
・「家庭裁判所」による審判
相続人間で協議が整わないときは、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。
「遺言書」による取得が一番確実です。
2.配偶者短期居住権とは?
夫や妻が亡くなったとき、その配偶者が今住んでいる家にとりあえず一定期間は住み続けられる権利のことです。
被相続人の家に無償(家賃を払っていない)で住んでいた配偶者が、遺産分割により居住建物の相続が確定した日または相続開始から6か月を経過したときどちらか遅い日まで権利があります。
2-1.配偶者短期居住権のメリット
・手続き不要
この権利は亡くなった人の配偶者がその家に無償で住んでいた場合、自動的に発生するので、すぐに家を出ていかなければならないと焦る必要がありません。 遺言や遺産分割の話し合いが始まっていなくてもオッケーです。
・とりあえず安心して住み続けられる
相続手続きが終わるまでは無償で住み続けられるので、急な引っ越しを迫られることがなく、特に高齢の配偶者にとっては安心です。
・登記不要
登記手続きがないことで、手間もなく費用もかかりません。
2-2.配偶者短期居住権のデメリット
・あくまで「短期間」の権利
遺産分割により居住建物の相続が確定した日または相続開始から6か月を経過したときどちらか遅い日までの権利なので、6か月ちょっとで消えてしまう可能性があります。
・ずっとは住み続けられない
長く住み続けるには、配偶者居住権を取得するか、家を相続する必要があります。
・相続人との関係によっては居住が難しくなる可能性がある
短期居住権が消滅した後、家の名義人から退去を迫られる可能性があります。
とくに、相続人の中に前妻との子がいるなど、家族関係が複雑な場合は要注意です。
・ずっと住み続けたい場合は新たな手続きが必要
被相続人の遺言がある、他の相続人との間の合意、家を相続、など別の要件を満たす必要があります。
3.まとめ
配偶者居住権は、残された高齢の配偶者を守る心強い制度ですが、万能ではありません。家族構成や、遺言、家の名義など、事前の準備をしておくことがとても大切だと思います。
まねきや不動産は不動産相続に特化した相続の専門チームです。
司法書士も在籍してあり、安心して相談ができます。
幸せな相続のために、今から準備しておきましょう。
どうぞお気軽にご相談ください!