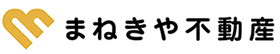法的に正しい遺言書作成のポイントとはなにか?
「遺言書」と聞くと、多くの人が「自分にはまだ早い」「財産家が作るものだ」といったイメージを持つかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。遺言書は、残されたご家族が遺産分割で揉めるのを防ぎ、遺言者が本当に望む形で財産を託すための重要なツールです。
そして何よりも、遺言書は大切な人への最後のメッセージといえるでしょう。
しかし、せっかくのメッセージも、法的な要件を満たしていなければ無効になってしまうリスクがあります。
そこで今回は、遺言書が無効になるリスクを解説するとともに、遺言者の意思が確実に実現されるためのポイントを、具体的にわかりやすくお伝えします。
1 遺言書が無効になる3つの主要なリスク
遺言書が無効になる原因はいくつかありますが、その中でも特に注意すべき3つの主要なリスクについて詳しく見ていきましょう。
1-1 形式不備による無効化:最も多い落とし穴
遺言書には、法律で定められた厳格な形式があります。たった1つの要件を満たしていなかっただけで、遺言書全体が無効になることも珍しくありません。
自筆証書遺言の場合、特に以下の3つの要件は絶対に守らなければなりません。
1-1-1 全文自筆であること
遺言書の本文はもちろん、日付や氏名、財産目録に至るまで、すべてを自筆で書く必要があります。パソコンで作成した書面や、他人に代筆してもらったものは無効です。
ただし、2020年の民法改正により、財産目録については自筆でなくてもよいことになりました。通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付できるようになり、作成がより手軽になりました。
しかし、この場合も財産目録の各ページに署名・押印が必要です。
1-1-2 日付の特定
「令和○年○月吉日」や「○月下旬」といった曖昧な表現は無効です。必ず「令和○年○月○日」のように、具体的な年月日を記載しなければなりません。
1-1-3 署名と押印
本文の最後に、本人が自ら署名し、押印する必要があります。押印は認印でも構いませんが、偽造を防ぐためにも実印を使うことが推奨されます。
公正証書遺言の場合は、公証人が作成するため形式不備のリスクは低いですが、「証人の欠格事由」には注意が必要です。未成年者や相続人、受遺者とその配偶者・直系血族は証人になることができません。
1-2 内容の不明瞭さ・矛盾による無効化
形式が正しくても、内容が曖昧だと遺産分割で争いが生じ、結果的に無効と判断されることがあります。遺言者の意思を確実に伝えるためには、遺言書の中に「誰に、何を、どのように」という点を明確にしておくことが重要です。
具体的には、以下の点に留意しましょう。
1―2-1 相続人・受遺者の特定
「長男に」と書くだけでは不十分です。同姓同名の人物がいたり、戸籍上の親子関係が複雑だったりするケースもあります。氏名、生年月日、続柄など、戸籍謄本に基づいて正確に、対象となる人物を特定しましょう。
1-2-2 財産の特定
「実家を長男に」といった表現もあいまいです。「実家」が何を指すのか、土地と建物の両方か、それともどちらか一方かが特定できません。
不動産であれば地番や家屋番号、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号まで、具体的に記載することが必要です。
1-2-3 あいまいな表現の具体例
たとえば、遺言書に「長男に全財産を遺す」と書いたとしましょう。このような書き方では、遺言書作成後に遺言者が取得した財産や、通帳に記載されていないタンス預金などの扱いで、相続人間で紛争が起きる可能性があります。
1-3 法的効力を持たない内容の記述
遺言書には、法律で定められた事項しか記載できません。それ以外の内容は法的効力を持たないため、記載しても実現されません。具体的には、以下の通りです。
1-3-1 遺留分(いりゅうぶん)の侵害
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には、遺産の最低限の取り分である「遺留分」が法律で保障されています。遺言書でこの遺留分を侵害した場合、遺言書自体が直接無効となるわけではありません。しかし、遺留分を侵害された相続人から、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。そうなると、結果的に紛争に発展してしまうため、注意が必要です。
1-3-2 義務を課す記述
「私のペットを世話すること」や「私の墓を守ること」といった記述には、法的な強制力はないので、この点も留意すべきです。
2 遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット
遺言書には主に3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自身の状況に合った形式を選びましょう。
2-1 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が、遺言書の全文、日付、そして氏名を自筆で書き、押印することで作成する遺言書のことです。
費用がかからず、いつでも手軽に作成できる点がメリットです。
一方、デメリットとしては、①形式不備で無効になるリスクが高い、②紛失、偽造、変造のリスクがある、③家庭裁判所の検認手続き(遺言書の有効性を確認する手続き)が必要で時間と手間がかかるといった点が挙げられます。
なお、2020年に法務局により遺言書保管制度が始まりました。この制度を利用すれば、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができ、紛失や偽造のリスクが減るうえ、検認手続きも不要になります。
2-2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が、遺言者本人の意思に基づき、公的な書類として作成する遺言書のことです。
2-2-1 メリット
メリットとしては、以下の点が挙げられます。
ア 形式不備で無効になるリスクがほぼない
公証人が作成するため、法的要件を満たした、間違いのない遺言書が作ることができます。
イ 紛失、偽造のリスクがない
原本は公証役場に保管されるため安心です。
ウ 検認手続きが不要
相続開始後、すぐに遺言書の内容を実行できます。
2-2-2 デメリット
一方、以下のようなデメリットが指摘されています。
ア 費用がかかる
公証人手数料が必要になります。遺産額に応じて変動しますが、数万円から数十万円程度が目安です。
イ 作成に手間と時間がかかる
公証役場との打ち合わせや、証人2人の手配が必要です。

2-3 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容は秘密のまま、存在を公証してもらう遺言書です。遺言者が署名押印した上で封印し、公証役場で手続きを行います。
遺言の内容を秘密にできるというメリットがある一方で、デメリットとして、①形式不備で無効になるリスクがある、②家庭裁判所の検認手続きが必要という点が挙げられます。
日本ではあまり利用されていません。
3 遺言書作成の具体的なステップと留意点
遺言書を完成させるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。
3-1 準備段階
準備段階として、以下のような作業が必要です。
3-1-1 相続財産の洗い出し
まずは、すべての財産をリストアップすることが必要です。不動産、預貯金、株式、有価証券、自動車、貴金属など、漏れがないように確認しましょう。借金などの負債も相続の対象となるため、正確に把握しておくことが大切です。
3-1-2 相続人の確定
現在の戸籍謄本を取得して、法律上の相続人を正確に把握する必要があります。認知した子や、養子縁組をした子も相続人になるため、漏れがないようにしましょう。
3-1-3 遺産の分け方を決める
誰に、何を、どれだけ遺すかを具体的に決めます。このとき、先に解説した遺留分も考慮に入れることが重要です。
3-2 遺言書の作成
遺言書の形式によって、以下の点に留意することが必要です。
3-2-1 自筆証書遺言の場合
鉛筆やシャープペンシルではなく、ボールペンや万年筆など、消えない筆記用具を使用するようにしましょう。消えやすい筆記用具を使った場合、後に遺言内容が不明瞭となり、争いの原因になりかねません。
3-2-2 公正証書遺言の場合
事前に公証役場に連絡し、必要書類(印鑑証明書、戸籍謄本など)や手続きの流れについて確認しましょう。証人2人の手配も必要となるので、依頼する人を決める必要があります。
3-3 作成後の留意点
遺言書を作成した後も注意しなければならない点があります。
3-3-1 遺言書の保管場所
自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用することが、紛失や偽造のリスクがなく、最も安全といえます。
自宅に保管する場合は、火災や紛失のリスクを考慮して、金庫や貸金庫を利用したり、信頼できる人に預けることを検討しましょう。
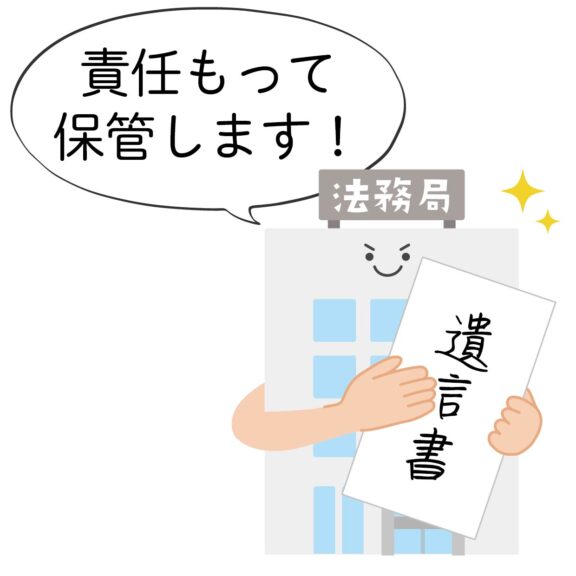
3-3-2 遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現する役割を担う人です。一般的には、相続人や弁護士などの専門家が指定されます。遺言執行者を指定しておけば、相続手続きがスムーズに進みます。
3-3-3 定期的な見直し
遺言書は一度作成したら終わりではありません。結婚、離婚、出産、相続人の死亡、財産の増減など、人生の状況は常に変化します。数年ごとに内容を見直す習慣をつけ、その時の家族状況に合わせて新たに作成することを検討しましょう。
4 まとめ
遺言書は、単なる財産分与のための書類ではありません。家族に伝えたい感謝の気持ちや、未来への願いを形にするためのものです。そして、遺言書の作成は、自分自身の安心だけでなく、残された家族の安心にもつながるものです。
無効になるリスクを回避し、また、後々の親族間の争いを防ぐために最適な遺言書を作成するためには、専門家の助言が必要です。遺言書を作成しようと考えた方は、一度弁護士などの専門家に相談しましょう。
まねきや不動産は、「相続不動産の困った」を丸ごとサポートする不動産会社であり、最初の相続相談窓口としてお客様に寄り添います。
遺言書を作成したいけれど誰に相談したらよいかわからないという方は、ぜひお気軽にまねきや不動産にお声がけください。