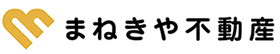遺産分割協議書のトラブルを防ぐために弁護士がチェックするポイント
相続は、家族が亡くなった悲しみの中で、財産という現実的な問題に向き合わなければならない、非常にデリケートなプロセスです。特に、複数の相続人がいる場合、「遺産分割協議」を通じて、亡くなった人(被相続人)の財産をどのように分けるかを話し合います。この話し合いで合意した内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。
一見すると、ただの合意内容をまとめた書類に過ぎないように思えますが、この協議書の作成を安易に進めると、後々深刻なトラブルに発展するリスクをはらんでいます。たとえば、「一部の財産が記載漏れだった」「代償金の支払い方法が曖昧だった」といった些細な見落としが、将来の紛争の火種となりかねません。
そこで今回は、遺産分割協議書作成時に見落とされがちなポイントを取り上げ、詳しく解説していきます。単に形式を整えるだけでなく、将来の法的リスクを回避し、相続人全員が納得できる円満な相続を実現するにはどうすればよいかについてお伝えします。
1 遺産分割協議書とは?その法的効力と重要性
はじめに、そもそも遺産分割協議書とはどのようなものかについて解説します。
1-1 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を相続人がどのように分割するか、その合意内容を明文化した書面です。
民法上、相続人全員の合意があれば、口頭でも遺産分割は成立しますが、不動産の名義変更や預貯金の解約といった各種相続手続きには、この書面の提出が求められます。
1-2 なぜ重要なのか
この書面は、単に手続きのために必要なだけでなく、将来のトラブルを未然に防ぐために極めて重要な役割を果たします。
相続財産が確定し、誰が何を相続するか、そしてどのような条件で分割するかが明確になることで、後から「話が違う」といった争いを防ぐことができます。
1-3 協議書の法的効力
相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書は、強い法的効力を持ちます。一度成立すると、原則としてその内容を撤回・変更することはできません。
もし、後から「やっぱり納得できない」と主張しても、他の相続人全員の同意がなければ、合意を覆すことは非常に困難です。だからこそ、作成段階での慎重な確認が不可欠となります。
2 弁護士が着目する!協議書作成前の重要ポイント
弁護士は、遺産分割協議書を作成するにあたり、まず、「誰が相続人か」「何が相続財産か」を正確に把握することから始めます。この事前調査を杜撰に行うと、どんなに完璧な書面を作っても無意味になってしまうからです。
2-1 相続人・相続財産の確定
以下では、相続人や相続財産の確定の段階でのチェックポイントについて解説します。
2-1-1 チェックポイント1:戸籍謄本の確認
弁護士は、遺産分割協議書を作成する前に、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続人を正確に特定します。
特に注意すべきなのは、被相続人に離婚歴があって前妻との間に子がいる場合や、養子縁組をしている場合です。
前妻との子や養子といった相続人の存在を無視して協議を進めても、その協議書は無効となり、後から大きなトラブルに発展します。
2-1-2 チェックポイント2:相続財産調査の徹底
不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などの負の財産もすべて洗い出す必要があります。見落としやすいものとして、名義預金(配偶者や子名義だが実質は被相続人の財産)、デジタル資産(SNSアカウント、仮想通貨など)が挙げられます。これらの財産を網羅的にリストアップすることで、遺産分割協議の土台が固まります。
2-2 遺言書の有無の確認
遺言書の有無の確認で重要な点は以下のとおりです。
2-2-1 チェックポイント3:公正証書遺言・自筆証書遺言の確認
被相続人が遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容が遺産分割協議に優先します。遺言書があることを知らずに分割協議を進めても、その協議書は無効となる可能性があります。
公正証書遺言は生前公証役場で作成されたものであり、発見後特段の手続は必要ありません。一方、自筆証書遺言は、原則として、家庭裁判所で検認手続きを行うなど、適切な手続きを経る必要があります。
3 ここが違う!弁護士がチェックする遺産分割協議書の書式と形式
遺産分割協議書は、単に相続人の名前と財産を書けば良いというものではありません。各項目に法的に有効な記述がされているか、弁護士は厳しくチェックします。
3-1 必須記載事項の確認
遺産分割協議書の必要事項として、以下の点を確認する必要があります。
3-1-1 チェックポイント4:タイトルの記載
タイトルとして「遺産分割協議書」と明確に記載されていることがまず必要です。
3-1-2 チェックポイント5:被相続人情報の正確性
被相続人の氏名、最後の住所、本籍、死亡年月日を、戸籍謄本や住民票通りの正確な情報で記載されていることも必要です。
3-1-3 チェックポイント6:相続人全員の情報の記載と合意
相続人全員の氏名、住所を正確に記載し、各自が署名・実印で押印することが求められます。押印は、印鑑証明書の印影と一致していることが必須です。一人でも欠けていると、その協議書は無効となります。
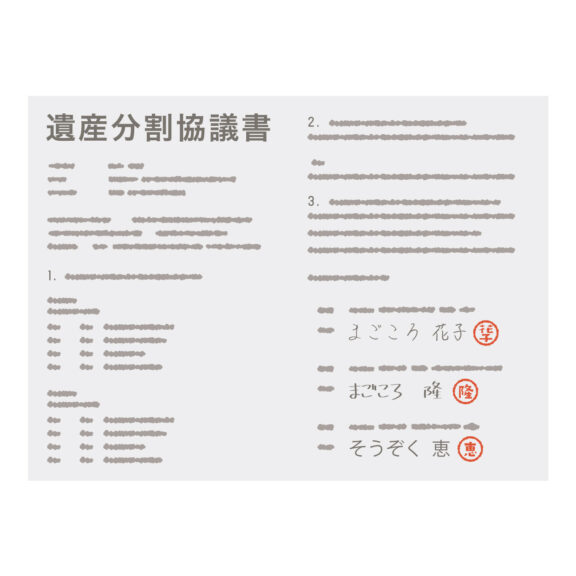
3-2 相続財産の正確な表記
遺産分割協議書に記載する財産は、将来のトラブルを防ぐため、正確に特定できるよう詳細に記述することが求められます。
3-2-1 チェックポイント7:不動産の表示
登記簿謄本通りに「所在」「地番」「地目」「地積」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などを正確に記載することが必要です。
3-2-2 チェックポイント8:預貯金の表示
金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期など)、口座番号、口座名義人を正確に記載します。評価額は、死亡日の残高を記載します。
3-2-3 チェックポイント9:株式等の有価証券の表示
銘柄、口数、評価額(死亡日の終値など)を正確に記載します。
4 トラブルを招きやすい具体的なケースと弁護士の対策
単に財産を分けるだけでなく、相続人間の公平性を確保するために、以下のような特別な事情を考慮する必要があります。
4-1 「特別受益」と「寄与分」
遺産分割協議書作成に当たっては、法定相続分だけでなく、「特別受益」や「寄与分」に配慮することも必要です。
4-1-1 チェックポイント10:生前贈与・学費援助などの考慮(特別受益)
一部の相続人だけが生前に多額の贈与や生活費の援助を受けていた場合、それを「特別受益」として、相続分を調整する場合があります。協議書にこの特別受益をどう考慮したかを明記することで、後々の不公平感を解消することができます。
4-1-2 チェックポイント11:介護や家業貢献の評価(寄与分)
長年にわたり被相続人の介護や家業の手伝いをしていた相続人は、その貢献分を「寄与分」として、他の相続人より多くの財産を相続する権利があります。寄与分をどのように算定し、協議書に反映させるか、弁護士が客観的な視点からアドバイスします。
4-2 換価分割と代償分割
遺産の中に不動産がある場合には、その分割方法も遺産分割協議書に記載する必要があります。
4-2-1 チェックポイント12:不動産の評価方法と売却後の分配(換価分割)
不動産を売却して現金で分配する「換価分割」の場合、売却後の税金や費用負担をどうするか、そして売却価格が想定より低かった場合の取り決めなどを遺産分割協議書に明記することが必要です。
4-2-2 チェックポイント13:代償金の取り決め(代償分割)
特定の相続人が不動産などを取得し、他の相続人に現金(代償金)を支払う「代償分割」の場合、代償金の金額、支払い方法、支払い期限を遺産分割協議書において明確に定めることが求められます。
これを怠ると、「いつまでもお金を払ってくれない」といった金銭トラブルに発展します。
4-3 相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合には、以下のような対応が必要です。
4-3-1 チェックポイント14:特別代理人選任の必要性
未成年の子も相続人となります。本来は、その未成年者の親が法定代理人となるはずですが、親自身も相続人である場合、利益相反(親が自分の取り分を増やすために未成年の子の取り分を減らすこと)が生じます。この場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任し、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加しなければなりません。
5 万が一のトラブルに備える!付帯条項の重要性
完璧な協議書を作成したつもりでも、後から予期せぬ事態が発生することもあります。弁護士は、将来のリスクを想定し、万が一に備える付帯条項を提案することができます。
5-1 弁護士が提案する付帯条項
弁護士が提案する主な付帯条項には以下のものがあります。
5-1-1 チェックポイント15:協議書に記載のない財産の取り扱い
弁護士は、遺産分割協議書を作成するにあたり、「本協議書に記載なき遺産が後日判明した場合は、改めて相続人全員で協議し、分割するものとする」といった条項を設けることで、後から見つかった財産についても円滑に手続きを進められるようにしておきます。
5-1―2 チェックポイント16:清算条項
弁護士が遺産分割協議書を作成する際には「本協議書に定める事項を除き、被相続人の遺産分割に関する相続人相互間の債権債務関係はないことを確認する」といった清算条項を設けることで、この協議書をもって遺産分割に関するすべての問題が解決済みであることを明確にし、後から新たな請求がなされることを防ぎます。
5-1-3 チェックポイント17:費用負担
協議書作成費用や不動産登記費用、相続税の申告費用などを、誰がどのくらいの割合で負担するかを明記することで、費用の分担に関するトラブルを回避するようにします。
6 まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を記録し、将来のトラブルから家族を守るための重要な書面です。しかし、その作成には、戸籍や財産の調査、各財産の正確な表記、そして将来のリスクを想定した法的条項の追加など、多くの専門的な知識が求められます。
自己流で作成した協議書は、一見問題ないように見えても、後から無効とされたり、金銭トラブルを招いたりする危険性を常に伴います。特に、相続人間で感情的な対立がある場合や、特別受益・寄与分といった複雑な事情がある場合は、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
相続というデリケートな問題を、円満に解決するために、遺産分割協議書作成の際は、弁護士に相談しましょう。
まねきや不動産は「相続不動産の困った」をまるごとサポートする不動産会社であり、少数精鋭の専門チームで、不動産の相続問題について解決を支援しています。
遺産分割協議書を作成したいけれど、誰に相談して良いかわからないなどのお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。