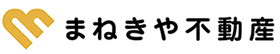空き家と相続~「負動産」としての空き家と相続の課題について
日本各地で、着実に空き家の数が増えています。総務省が発表した2023年の「住宅・土地統計調査」によれば、国内の空き家率は過去最高の13.8%に達し、全国の住宅の約7軒に1軒が空き家という状況です。
この数字は、単なる統計上の問題ではありません。適切に管理されない空き家は、地域の景観を損ねるだけでなく、倒壊の危険性や不法投棄、治安悪化の原因となり、私たちの暮らしに直結する深刻な社会問題となっています。
空き家問題は、しばしば地方の過疎化や人口減少などと結びつけられますが、その根幹には、多くの場合「相続」の問題が結びついています。
先祖代々受け継がれた大切な家が、次世代にとっては「資産」ではなく、維持管理のコストや精神的負担を伴う「負動産」と化してしまう現実があります。
今回は、なぜ相続が空き家を生み出す主要な要因となっているのかについて多角的に分析し、その解決に向けて、個人と社会がそれぞれどういったことに取り組むべきか解説します。
1 空き家問題の現状と社会的コスト
空き家が増加している背景には、①高度経済成長期に大量に供給された住宅が、寿命を迎えつつあることに加え、②人口減少や都市部への人口集中といった社会構造の変化が挙げられます。
特に地方や郊外では、住宅の需要と供給のバランスが崩れ、住む人がいなくなった家が、そのまま放置される事態が頻繁に起こっています。
こうした空き家は、時間の経過とともに老朽化が進み、やがて「特定空き家」と呼ばれる危険な状態に陥ります。「特定空き家」とは、2015年に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、自治体が指定する、特に問題が深刻な空き家のことです。
屋根や壁が剥がれ落ち、雑草が繁茂し、害獣の棲み処となるだけでなく、台風や地震といった自然災害時には倒壊の危険もはらんでいます。近隣住民は、「特定空き家」のために常に不安を抱えることになり、地域の安全・衛生環境が著しく損なわれることとなります。
さらに、空き家問題は経済的な損失も招きます。空き家が増えれば、その地域の不動産価値全体が下落し、地域の活力が失われていきます。自治体にとっては、住民税や固定資産税の徴収機会が減少し、行政サービスの維持が困難になるといった問題もあります。
管理が行き届かない空き家が、地域全体に問題を引き起こす「負動産」となっているのです。
2 相続が空き家化を招く3つの要因
空き家はなぜ「負動産」となるのでしょうか。
実は、その核心には「相続」の問題が絡んでいます。相続人が存在してもなお、家が放置される主な要因として、以下の3つが挙げられます。
2-1 要因1:共有相続による意思決定の停滞
実家を相続する際、故人に配偶者や子供が複数いれば、その家は相続人全員の「共有財産」となります。そして、日本の民法では、共有財産を処分する場合、原則として共有者全員の合意が必要です。
しかし、相続人それぞれが遠方に住んでいたり、多忙であったり、あるいはその家に対する思い入れが異なったりすれば、全員の合意形成は極めて困難となります。
相続財産を売却することについて反対する相続人がひとりでもあれば、その家は活用することも処分することもできずに、放置される事態にとなります。結果として、誰も積極的に関わらないまま、年月だけが過ぎていくのです。
2-2 要因2:経済的・心理的な葛藤
多くの相続人が直面する経済的な課題が、固定資産税の特例措置です。
現在の税制では、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に減額されます。しかし、家屋を解体して更地にしてしまうと、この特例が適用されなくなり、税負担が増大します。
相続人にとっては、誰も住んでいない家でも、「壊すと税金が高くなる」という経済的な理由から、あえて放置を選択してしまうことになるのです。
また、心理的な葛藤も大きな要因です。「親との思い出が詰まった家を壊すのは忍びない」「家を処分したら親不孝だと思われそう」といった感情は、合理的な判断を妨げる大きな壁となります。金銭的な問題が解決してもなお、この心理的なハードルを乗り越えられない人が少なくありません。
2-3 要因3:所有者情報の不明確さ
相続が発生しても、所有権の移転登記が行われないケースは少なくありません。特に、相続する不動産に資産価値が認められない場合や、手続きが煩雑であることから、登記を放置してしまう人が少なくありません。そのため、年月を経て所有者がわからなくなり、管理や処分をしようにも、誰に連絡を取ればよいか不明な状態に陥ることとなります。
行政が指導や勧告を行おうとしても、その相手を特定できず、やむなく放置され続けるという悪循環が生まれるのです。
3 空き家問題解決に向けた制度の動向
こうした相続に起因する空き家問題に対し、国や自治体も対策を講じてきました。
3―1 空き家対策特別措置法
代表的なものが、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」です。この法律により、自治体は管理不全な空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に対し、解体や修繕を命令できるようになりました。
命令に従わない場合、固定資産税の特例を解除し、税負担を増やすことで所有者に管理を促す仕組みが導入されたのです。しかし、特定空き家に指定するまでには多くの調査と手続きが必要であり、すべての空き家に対応するには行政のマンパワーに限界があるという課題が残されています。
3-2 相続登記の義務化
より根本的な対策として、2024年4月1日から「相続登記の義務化」が開始されました。これまでは相続登記は任意でしたが、今後は相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を完了させることが義務となります。正当な理由なく怠った場合には過料が課せられる可能性もあります。
この制度の施行により、長年にわたり放置されてきた所有者不明の不動産問題が少しずつ解消され、空き家への対応が円滑に進むことが期待されています。
3-3 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続した空き家を売却する際に利用できる税制優遇措置も存在します。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。この制度は、相続した家を早期に売却し、活用を促すための重要な支援策ですが、その存在自体が十分に知られておらず、活用に至らないケースも多いのが現状です。
4 個人と社会が取り組むべき解決策
空き家問題の解決には、法制度の整備に加え、私たち一人ひとりの意識改革と行動が不可欠です。
4-1 個人の取り組み
個人の取り組みとして最も効果的な対策は、「相続は、親が元気なうちに」という意識を持つことです。
親との間で、不動産を含めた財産について事前に話し合う「家族会議」を持つことが重要です。その際に、家をどうしたいか、誰が引き継ぐかといったことを明確にし、エンディングノートなどを活用して意思を残しておくことが、将来的なトラブルを防ぐ最善策となります。
また、相続財産に不動産が含まれる場合は、早い段階で司法書士や不動産業者、税理士といった専門家に相談することが賢明です。専門家は、法的・経済的な観点から冷静にアドバイスを提供し、最適な解決策へと導いてくれる頼れる存在です。
4-2 社会全体の取り組み
より根本的な解決には、制度のさらなる見直しが求められます。特に、「固定資産税の特例」は、空き家を放置するインセンティブを与えているとの批判が根強く、その見直しを求める声が高まっています。
適切に管理されていない空き家に対しては、税負担を段階的に引き上げるなど、所有者に責任を促す仕組みが必要です。
さらに、行政と民間事業者が連携し、空き家を地域資源として再活用する取り組みを強化することも重要です。空き家バンクの機能を強化し、移住希望者と空き家を結びつけたり、リノベーションや賃貸活用をサポートするモデルを構築したりすることで、空き家を「負動産」から「地域の未来を創造する資産」へと転換させることが可能になります。
5 最後に
空き家問題は、単に建物をどうするかという問題ではなく、社会が直面する人口動態の変化、法制度の複雑さ、そして家族間のコミュニケーションといった多岐にわたる課題が凝縮されたものです。根本に相続というプロセスが深く関わっている以上、問題解決には、個人の心構えと社会全体の制度改革の双方が必要です。
次世代に「負動産」を残さないためには、家を「単なる財産」としてではなく、「地域の財産」として、「管理する責任」を伴うものとして捉え直すことが不可欠です。
相続が発生する前からの計画的な話し合って、既存の制度を有効活用し、そして必要に応じて制度の変革を求めていくことが、解決のために求められます。この粘り強い取り組みこそが、空き家問題を解決へと導き、住みやすく、活力ある社会を築いていくための確かな一歩となります。
まねきや不動産は「不動産の相続の困った」をまるごとサポートする不動産会社です。空き家になっている相続不動産についても、どうぞお気軽にご相談ください。不動産の専門家が「負動産」になる前にしっかり対応できるようお手伝いします。