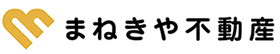円満な不動産相続の進め方
不動産は、家族の歴史が刻まれた大切な資産です。しかし、その「大切な資産」が、時として家族間の深刻な対立の火種になってしまうことがあります。円満な相続とは、単に財産を法律どおりに分けることではなく、家族の絆を未来へつなぐことといえます。そのためには、適切な知識と、何よりも事前の準備が不可欠です。
本稿では、不動産相続をめぐるトラブルの核心や生前に行うべき対策、相続発生後の具体的な手続き、そして円満な解決を実現するための心構えなどについて詳しく解説します。
1 なぜ不動産相続は揉めるのか?〜トラブルの核心
不動産は、現金や預金と異なり、そのままでは公平に分けることが難しい財産です。この特性が、揉める最大の原因となります。
1-1 不動産の特性と「揉める」リスク
ここでは、不動産にどのような特性があり、どうして不動産相続が揉めるのかについて解説していきます。
1-1-1 分割の難しさ(換価分割、代償分割、共有名義の選択肢と課題)
不動産を相続する方法は主に4つあります。
ア 現物分割
特定の相続人が不動産をそのまま取得する方法。
イ 換価分割
不動産を売却し、売却代金を分割する方法。
ウ 代償分割
特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に現金を支払う方法。
エ 共有名義
相続人全員で不動産を共有する方法。
このうち、換価分割や代償分割を選択する場合、不動産の価値をどう評価するかで意見が対立しやすいという問題があります。また、安易に共有名義にすることを選択すると、将来の売却や建て替えの際に、共有者全員の同意が必要となり、長期にわたりトラブルが生じるリスクがあります。
1-1-2 評価額の認識のズレ
不動産には、固定資産税評価額、相続税評価額、そして時価(市場価格)など、複数の評価基準が存在します。遺産分割協議では、どの評価額を採用するかで意見が分かれることがあります。
自宅に住み続けたい相続人は低く評価したがる一方、現金を多く受け取りたい相続人は高く評価したがる、といった感情的な対立が生まれやすいのです。
1-1-3 特定の相続人の居住に対する感情的な価値
特に被相続人(亡くなった方)が居住していた自宅は、単なる財産としての価値だけでなく、家族の思い出や歴史が詰まった「感情的な価値」を持ちます。この感情的な価値が、合理的な分割を妨げ、意見の対立をさらに深刻化させることが多々あります。
1-2 予備知識の不足と情報格差
相続に関する知識が不足していると、誤解や不信感を生む原因となります。
また、特定の相続人が被相続人の財産を管理していた場合、他の相続人との間に情報格差が生まれ、「私だけ隠されているのでは?」といった疑念が生じ、トラブルを加速させます。
2 生前に行う円満な不動産相続のための準備
円満な不動産相続を実現することは、相続が起きる前にどれだけ対策を講じられるかにかかっています。生前対策は、①トラブル防止、②節税、③納税資金の確保という3つの目的を持っています。
2-1 財産の「見える化」と情報共有
以下では、生前の不動産相続対策として必要な財産の「見える化」と情報共有の重要性について解説します。
2-1-1 所有不動産の正確な把握
まずは、所有不動産を正確に把握することから始めます。
ア 名寄帳(なよせちょう)の取得
市区町村役場で取得できる名寄帳には、その市町村内にある所有不動産の一覧が記載されています。登記し忘れていた不動産や、故人名義のままになっている土地などを発見できます。
イ 登記簿謄本・固定資産税納税通知書の確認
登記簿で持分や権利関係を確認し、納税通知書で固定資産税評価額を把握します。
2-1-2 家族会議の重要性
財産の状況が把握できたら、それを相続人となる家族と共有することが最も重要です。
「誰に何を相続させたいか」「自宅に住み続けたい人がいるのか」「不動産の評価額の考え方」などを率直に話し合うことで、相続人全員が共通の認識を持ち、不信感を解消することができます。また、生前に被相続人が示した意思は、後の遺産分割協議において、大きな指針となります。
2-2 最強のトラブル回避策「遺言書」の作成
遺言書は、被相続人の最終的な意思を示すもので、強力なトラブル回避策となります。遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要となり、不動産を「誰に」「どれだけ」相続させるかを明確に指定できます。
2-2-1 公正証書遺言を推奨する理由
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言などがありますが、特に不動産を含む相続においては、以下の点から「公正証書遺言」の作成が望ましいでしょう。
ア 形式不備の回避
公証人が関与するため、法的に無効になる心配がありません。
イ 検認手続きが不要
家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続開始後の手続きがスムーズです。
2-2-2 遺留分への配慮の重要性
遺言書を作成する際には、兄弟姉妹以外の法定相続人の最低限度の取り分である「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
遺留分を侵害する内容であっても遺言は有効ですが、遺留分権利者から「遺留分侵害額請求」を受けると、金銭の支払い義務が生じ、かえって新たなトラブルを招く可能性があります。遺言書作成時には、必ず弁護士などの専門家に遺留分の計算を含めて相談しましょう。
2-3 相続を見据えた不動産の整理・組み換え
不動産を現金化することで、相続人全員に公平に分割しやすくなります。
2-3-1 共有名義の解消や不要な不動産の生前売却
活用予定のない不動産は、生前に売却し現金化することで、分割しやすく納税資金にも充てられます。
2-3-2 代償分割資金の準備
特定の相続人に自宅を相続させたいが、他の相続人に代償金を支払う現金がないというケースが多々あります。この代償金を賄うために、生命保険の受取人を自宅を相続しない相続人に指定しておくなど、事前に資金を用意しておく対策も非常に有効です。
3 相続発生後の具体的な進め方
生前に対策ができていなかった場合でも、相続開始後の手続きを冷静かつ迅速に進めることで、円満解決につながります。
3-1 相続開始直後の対応と情報の収集
ここでは相続開始直後に必要な対応や情報の収集について解説します。
3-1-1 法定相続人の確定
はじめに、相続人を正確に確定させる必要があります。被相続人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍謄本を取り寄せ、養子や隠し子などの有無を確認します。相続人がひとりでも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効となるため、この作業は厳密に行う必要があります。
3-1-2 相続財産の再確認
不動産については、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得し、評価額を確認します。
借金や負債が多い場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述し、「相続放棄」を検討する必要があります。
3-2 遺産分割協議の進め方と円満合意のポイント
遺言書がない場合、または遺言書で分割方法が指定されていない財産がある場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。
3-2-1 冷静な話し合いの場の設定
協議の場では、感情論を避け、冷静に話し合う姿勢が求められます。
相続人それぞれの生活状況や将来の希望(自宅に住みたい、現金が必要など)を尊重し、互いに耳を傾ける姿勢が重要です。
また、不動産は分割が難しい財産であるため、その後の管理や利用まで見据えた上で、現物分割、代償分割、換価分割のいずれが最も妥当か、話し合いましょう。
3-2-2 専門家の活用と中立的な意見の導入
協議が難航しそうな場合や、不動産の評価が複雑な場合は、弁護士や司法書士、不動産鑑定士といった専門家を交えて協議することが、円満解決につながります。客観的かつ中立的な意見を提示してもらえるため、感情的な対立を収束させる助けとなります。
3-3 遺産分割協議書の作成と実務手続き
協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
3-3-1 遺産分割協議書の法的効力
遺産分割協議書は、不動産の特定、誰が何を相続するか、代償金の金額などを明確に記載し、相続人全員が署名し、実印で押印することで、法的な効力を持ちます。後の相続登記や預貯金の解約手続きに不可欠な書類となります。
3-3-2 相続登記(名義変更)の手続き
不動産を取得した相続人は、法務局に申請して名義変更手続き(相続登記)を行うことが必要です。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続の開始を知った日から3年以内に登記をしないと過料の対象となる可能性があるため、速やかに手続きを進める必要があります。
3-4 相続税の申告と納税
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
不動産を相続する場合、特に居住用宅地については、一定の要件を満たせば土地の評価額が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。この特例を適用するためには、相続税の申告が必要なため、適用要件をよく確認し、税理士と連携して進めましょう。
4 円満相続を実現するための専門家の活用
専門家は、単に手続きを代行するだけでなく、家族の対立を緩和する役割も担います。
生前対策の段階では、遺言書の作成、納税資金の試算、不動産の評価、節税対策などについて、税理士や司法書士に相談することにより、有効な対策を立てることができます。
一方、相続発生後に遺産分割協議が膠着した場合には、弁護士を介入させることで、法律に基づいた客観的な解決案を提示してもらうことができます。
専門家を交えることで、家族の感情的なぶつかり合いを回避できることが最大のメリットといえます。
5 最後に
不動産相続で揉めないためには、準備が欠かせません。遺言書の作成、財産状況の「見える化」、そして何よりも家族との率直な対話が必要です。
「円満な相続」とは、亡くなった人が残してくれた財産を、家族が争うことなく受け継ぎ、そしてその後の人生を円満に過ごせるようにすることです。
そして、不動産の円満な解決を目指すためには、信頼できる専門家に相談することが有効です。
まねきや不動産は、相続に特化した不動産会社であり、専門家を交えた少数精鋭のチームで、相続に関わる様々な手続きをワンストップでサポートします。
円満な不動産相続を目指して準備をしたいけれど誰に相談したらよいかわからないという方は、ぜひまねきや不動産にご相談ください。